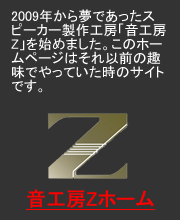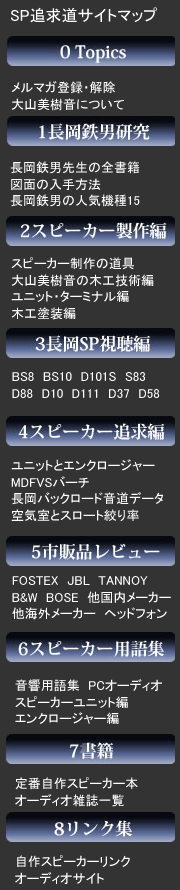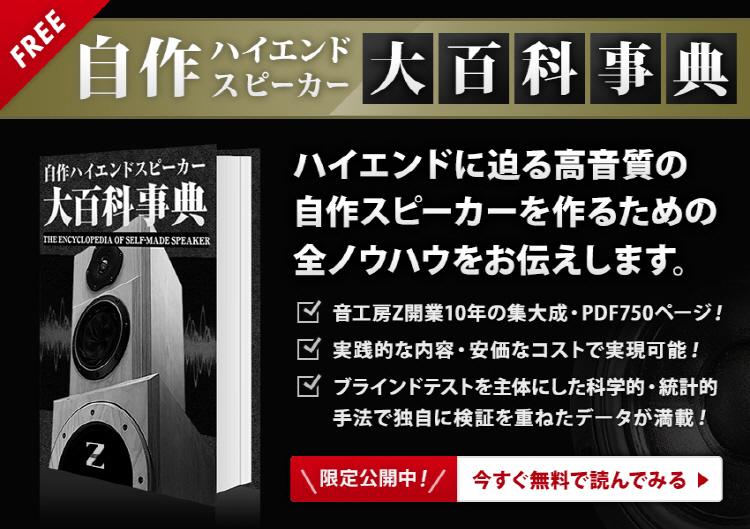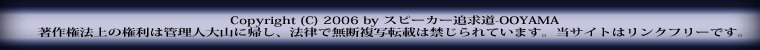TANNOY WESTMINSTERの視聴・評価

TANNOY ウエストミンスター視聴後の大山の評価
現代版のオートグラフである「ウエストミンスター」は400万以上のウルトラハイエンド系に属するスピーカー。特注生産です。店頭でもほとんど見かけません。
ウエストミンスターの内部音構造について。詳しいデータはないがカタログには音道約3mと書かれている。ちなみに長岡鉄男先生のバックロードホーンはD101Sスーパースワンが2m42センチ。D58ESが2m77センチ。それらに比べると若干長めの設計なのが分かる。バックロードはいろいろ見てきたが、3m以上の長さの音道をとるとどうしても低域の遅れが目立ち、ソースを選んでしまう印象がある。弦楽器やボーカル(オペラ系)オンリーであればもう少し長くても問題ないかもしれないが、破裂音(太鼓やティンパニー)が多いソースだと3mでも長すぎると感じる場合もある。しかしこれらはユニットと箱の組み方によっても変わるから一概に言えることでもない。タンノイのウエストミンスターのホーンは弦など持続音系の楽器にチューニングの焦点が合うような気がする。
あとこれはデータの上での話しではないが、ホーン開口部がユニットの大きさの割りに比較的狭い。これはホーンの開く率をエクスポネンシャルのルールにそのまま適用しているのではないか?ちなみに長岡バックロードは、空気室、スロート、第一音道部分、第2音道部分ぐらいまでは、開き率とそれ以降の開き率に差をつけている。これをカスケードホーンと呼ぶ。こちらのほうがホーンとしての能率は下がるが、スムーズな特性を得られる。つまりウエスとミンスターはホーンとしての能率を重視しているためこの異常に高い99db(w/m)という能率を達成しているのかもしれない。
一つだけ気になるのはタンノイのユニットはカタログを見ると大きく分けて、アルニコを使うか否かで2つに大別している。アルニコ版には口径が25、30、35の3種類を用意している。しかし、バックロードとフロントロードをデュアルで駆動するユニットと、バスレフ用のユニットが全く同一のものであるというのはちょっと考えにくい。何らかのチューニングを施しているのだろう。
このスピーカーを視聴したのは数年前とある中古オーディオショップにあり、音を聞きました。ゆったりした壮大な音だけが印象に残っています。1週間後に行ったらもう誰かが購入してなかったのを覚えています。
★楽天で最安ショップ順にタンノイウエストミンスターロイヤルの値段を調べる★
タンノイ ウエストミンスターカタログより特徴
- 同軸2wayフロント+バックロードホーン(38センチ)
- クロスオーバー周波数1khz
- 周波数特性~22khz
- 能率99Db(Wm)
- 寸法(W×H×D) 980*1395**560
- 内容積530L
- 138kg