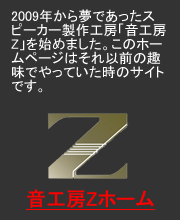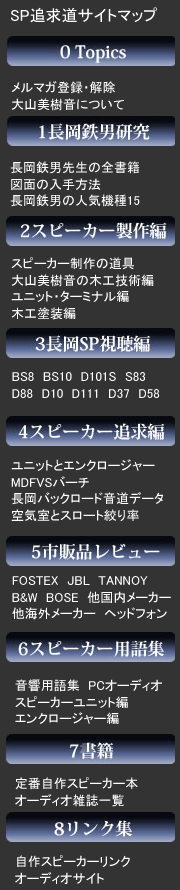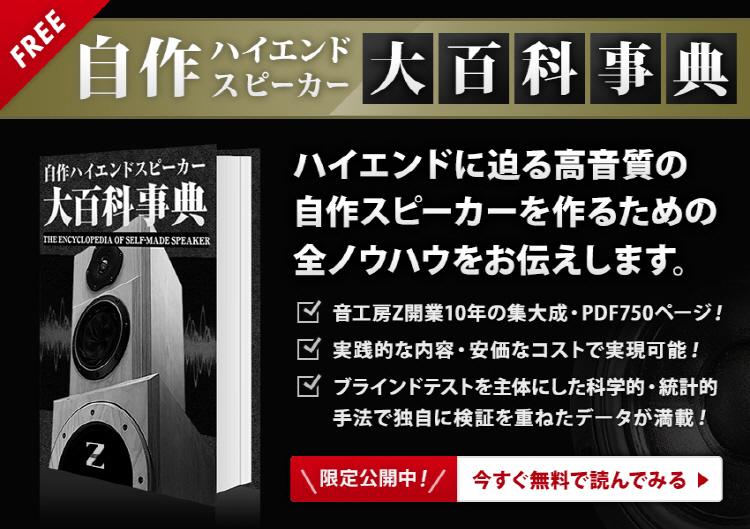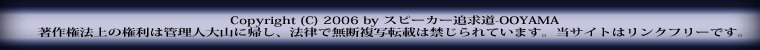スピーカー追求道>【3長岡SP視聴編】D-10バッキートップ>
常識はずれのバックロードバッキー
基本条件+シナ合板キャビネット+FE103E
まずは長岡鉄男式バックロードの音道構造のデータD-10を見て欲しい。私が長岡鉄男師のバックロードホーンスピーカーのデータをひとつづつ計算してだしたものだ。まず最も注意を引くのが「ホーン全長」これがスーパースワンやD-55など主要スピーカーで2m50ほどであるのに対して、バッキーは僅か1m75センチしかないという点である。ホーン長が短い影響は低音がでにくくなり、f0付近で特性にあばれがでるといわれている。ただしホーンからでる低域とユニットからでてくる音の時間差(つながり)は良くなるというメリットもある。
次に直管の形状。それまでの長岡師のスピーカーでは直管でバックロードの設計をする時に、5,6つの音道部にホーンを分け1つ1つのホーン長を違う長さにしていた。それはおそらく定在波の影響を避けるためにそうしていたのだろうが、バッキーではホーン長さ40センチのを5つ合わせて「ホーン全長1m75」としている。これではホーンからの音にすさまじいクセがでるのではないかと長岡師も懸念していた。さらにクロスがオーバー250hzと私が調べた中で最も高い。これはどういうことかと比較的高い音域までホーンロードをかけ、いわば中高音にもホーンロードをかける。これは長岡鉄男師のバックロードホーンの常識「ホーンからの中高音の漏れを防ぐ」から遠ざかることになるのではないか。特徴をまとめると
- ホーン全長が短い ⇒低音がでない
- ホーン音道部が直管、全て360度での折り返し ⇒エンクロジャー内部で定在波が発生しやすくなる。
- クロスオーバー250hz⇒ホーンから中高音が漏れる。定位が悪化する。
長岡鉄男師のバックロードホーンは音道構造を調べて分かったが、人気のあるスピーカーはそれなりの公式があり、全てり理屈にかなった設計がなされているのだが、どうやらこのD-10だけはオーソドクスからは外れた異色のスピーカーのように思える。試聴してみると分かるが、決して上に上げたマイナス面は感じられず、素晴らしい音にまとまっているのがこのスピーカーで、非常に人気の高いスピーカーだ。バックロードは「密閉と共鳴管と後面開放を混ぜ合わせた複雑なシステムである」とどこかで読んだが、このスピーカーは摩訶不思議なバックロードを象徴しているような気がする。
 |
| D-10backie |