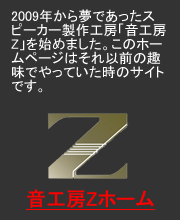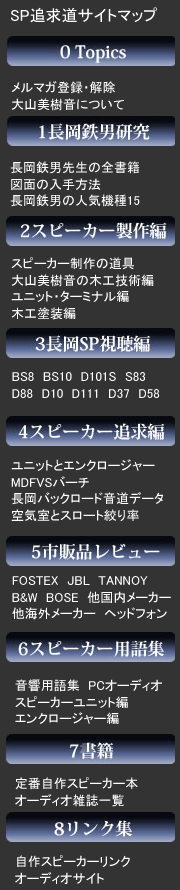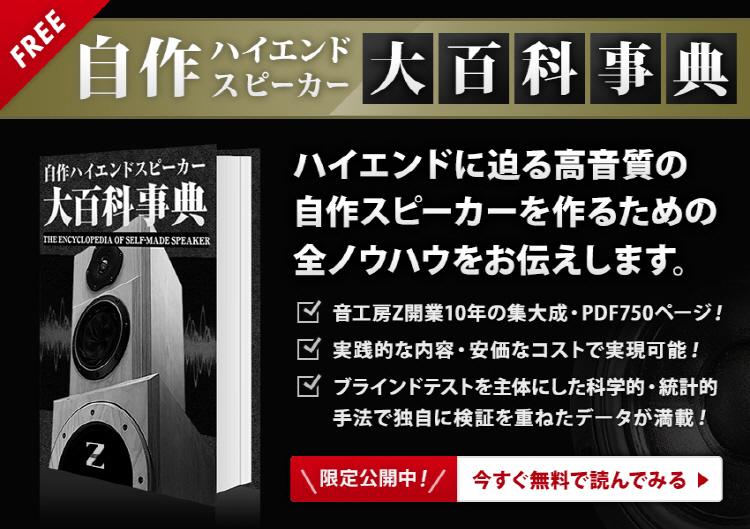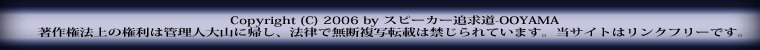JBL 4312Dの視聴・評価

JBL 4312D視聴後の大山の評価
JBLの4312シリーズは43**シリーズのエントリーモデルで、歴史が長く数え切れないほど様々なバージョンが生まれ販売されてきた。初代4311は70年代に4312は80年代の発売で、現在の4312にいたる。次に上げるのは4312のバージョンを示している。4312⇒ 4312A ⇒4312XP ⇒4312B ⇒4312MK2 ⇒4312BMK2 ⇒4312SX ⇒4312D。
43**シリーズはシリーズ最上級の4343(現在は4348)から廉価版の4312まで現在5機種あり同一のスタジオモニターというとで共通項もあるが、違う点も多々ある。共通項はJBLの伝統を愚直に守っているの一言につきる。いわくJBLのトレードマークである30センチ以上の大型ウーファーからでる芯のある低音。バス・ドラム・ピアノのアタック感をリアルに表現する点。上位機種にはミッドにSonoglassホーン搭載でサックス・トランペットの独特な表現など。後の違いは他のJBLのレビューをみていただきたい。
ではこの4312Dの特徴は何か?、一番大きな特徴はウーファーをスルー接続(通常はコイルをはさんでハイカットを行うのをネットワークなしでミッドとついなぐこと)させているといういうこと。これは4312シリーズの伝統のようになっている。結果クロスを結構高めにとっているのだがミッドと少々帯域がかぶる。しかし鳴りっぷりのよさはある種自作の完全ネットワークなしのスピーカーを彷彿させるものがある。
4312には上位モデルにあるミッドのホーンはもちろん付属しないが、エントリーモデルとしては十分なほど低域のメリハリ、切れはある。この機種はいやというほど視聴を繰り返してきたので、聴かなくても分かる部分も大きいが、バス・ドラム・ピアノの低域の量感はやはりJBLでしか味わえない魅力がある。4312の音の傾向はこのシリーズはある意味愚直に伝統的なJBLの味を守っていて、現代的なS9800シリーズのハイエンドモデルとは音の傾向はかなり違う。個人的には(いや他でもコンセンサスはできていると思うのだが・・)ジャズ向きで、繊細な表現をするクラシック向きではないと思う。
自作で小口径を中心にやっていると4312のボーカル帯域の音のにごりは少し気になるが、30センチクラス系の口径を今まともにやっているメーカーはJBLぐらいになってしまったのを考えると、20万程度の予算、大口径好みの人にはこれしか選択肢がないとも言える。 しかし、10年、20年くらい前はこのような30センチクラス系のウーファーが市場を席巻していたのを考えると現在(2007年)は小口径圧勝(長岡先生圧勝??)の時代になってしまったのはしみじみ感慨深いものがある。
楽天で最安ショップ順にJBL 4312Dの値段を調べる。
JBL 4312Dカタログより特徴
- アルミダイキャスト製高剛性エアロダイナミックフレームNDD方式の磁気回路2213Nd搭載
- 高分子ポリマーコーティングコーン採用の125mmミッドレンジ105H
- ピュアチダンドーム054Ti
- 3ウエイバスレフ(300mm×1、125mm×1、25mm×1)、
- クロス2khz、5khz
- 寸法(H×W×D)597*362*299
- 17k